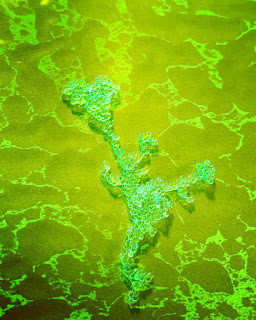私が制作の理論としているのが支持体論というものです。これは「すべての存在は、より高次元から見ると何か別のものを形作るための支持体(材料)としても存在する」という言葉でこれまで説明してきました。この考えは、知覚も認識もできないような事柄を中心主題にしようと感じたからです。今回は、なぜそのような荒唐無稽で夢想的なことを考え、制作していくことが重要なのかについて語ろうと思います。
私は平成1年の生まれなのですが、その頃というのは丁度世の中が先行き不透明な時代に突入する時代でもありました。世界でいえばソ連が崩壊し、大きく世界を二分していた片方の「真実」が転覆してしまいました。また国内でいえばバブルが弾けて、それまで右肩上がりであった日本の成長経済が停滞していきました。その後も阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件など国内に激震が走る大事件が起こり、国外では9.11、それに伴う新興武装勢力とテロリストの脅威などが続き、リーマンショックによる更なる不況、3.11の未曾有の大災害と原発問題の暴露…その他にも予想だにしない脅威と被害を受けた事件がいくつも重なってきました。そして現在、私たちは新型コロナウィルスによるパンデミックの渦中に身を置いています。
こうした予想だにしない事柄がこの30年の間に、かなり頻繁に繰り返されているように思われます。2010年頃からビジネスシーンでも使われるようになったVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)という言葉にも表されるように、社会や経済がとても不安定で見通しの効かない状態であることは、皆さんも感じられることだと思います。また人間の活動が地球に与える影響により、異常気象や環境破壊などの様々な問題がより深刻化していきました。そして2016年に国連が掲げたのが、持続可能な開発目標のSDGsであり、その中に環境問題への取り組みも入っています。更に哲学の世界では、しばしば思弁的実在論と総称されるいくつかの新しい存在に対する考え方も現れ、そこでは主に人間以外の存在や、人間が存在しない世界への考えが論じられています。そして科学の世界は加速度的に技術革新が進められ、社会の中で中心主題となりやすいのが人工知能AIの開発でしょう。これは技術的特異点シンギュラリティ(AIが更に有能なAIを作り出す)という予測が立てられるほど、人間に対して根本的な存在意義に影響を与えるものとなっていきます。
つまりこの十数年間というのはより一層、人間が生きていくためには人間以外の存在に対する思考を深める取り組みが必要だとされてきたのです。私は2014年の修士論文の一部に今後の展望として、人間が関わりあうことのないであろう世界や存在に対する眼差しを述べていたのですが、今思えばその頃は制作の中心主題をなるべく自分事から遠ざけようと客体化していった延長上のものくらいにしか思っていなかったのですが、現在になってようやくこうした社会の動勢に影響されたものであったと感じられるのです。
ここでやっと本題としての、なぜ今支持体論なるものを思考しながら制作するのかというと、激烈な変化が加速度的に進んでいる現代社会において、あらゆる事象や存在をこれまでのような人間を中心とした視点から活動するのではなく、そこにあるかもしれない不確定で曖昧で知覚も認識すらもできないような事柄を察しながら、現在目にしているあらゆる存在や現象に対し、全く別のイメージや感覚、考え方などをレイヤーのように重ねながら捉えることで、これから先の未来へのワクチンのような働きをするのではないかと考えるからなのです。
人間以外をテーマとした作品や取り組みは現在たくさん存在しており、一つのトレンドとも言えるでしょう。例えば動物や植物などから見た人間や地球などへの人類学的なアプローチや、科学技術を全面に扱った新しいフォーマットやアウトプットなどです。それらはとてもラディカルかつ魅惑的な求心力を持っているのですが、私は自らがそうしたジャンルの中に身を置くのではなく、少し距離を置いた外側から俯瞰的にその状況を眺めていたいのです。なので支持体論という存在のあり方を思考したり、あくまでも美術作家として作品を形作ることを通して物事を捉えたりアウトプットしたりするのです。そしてまたそれらから新たなアプローチを発見したり試行したりしながら、自分の生きた時代を象徴するような作品を作りたいと願っているのです。
今後も予測不可能で複雑怪奇な事件や変化に、人間は更に頻繁に立ち会うこととなっていくでしょうが、作家はそうした情勢をいかいして自らの思考と感覚ですくい上げ、それぞれのメディアに落とし込んで人々と共有できるのかを実践する必要があります。美術の場合は全くの共有とはならずとも、いかにして人々の感覚に引っかかるものを与えられるのかということになるかもしれません。
次回は現在の制作を具体的に取り上げながら、私の思う、作品とそれが示す思考や知覚の揺さぶりなどについて語りたいと思います。